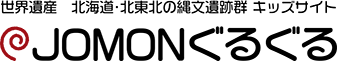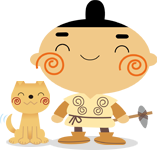大湯環状列石[おおゆ かんじょうれっせき]

[おおゆ かんじょうれっせき]


大湯環状列石(おおゆ かんじょうれっせき)は、万座(まんざ)と野中堂(のなかどう)という、2つの環状列石(かんじょうれっせき)を合わせたよび名です。環状列石(かんじょうれっせき)とは、石を丸くならべた遺跡(いせき)で、「ストーンサークル」ともよばれ、お墓や、マツリのための特別な場所だったと考えられています。
大湯環状列石(おおゆかんじょうれっせき)では、10数個の石をならべた円形や四角のかたまりが、いくつもならべられています。この小さなかたまりのひとつひとつが、お墓だったようです。万座環状列石(まんざ かんじょうれっせき)では約5000個、野中堂環状列石(のなかどう かんじょうれっせき)では約2200個の、川の石が使われています。
環状列石(かんじょうれっせき)のまわりには、掘立柱(ほったてばしら)建物や、食べものを入れておく貯蔵穴(ちょぞうけつ)などが見つかっていて、すぐ近くで人々が生活していたようです。同時に、土偶(どぐう)やキノコの形をした土製品(どせいひん)など、日常では使わない道具もたくさん見つかりました。これらは家族が長く幸せでいることを願ったり、自然への感謝を表したりしていると考えられています。


遺跡(いせき)のまわりの景色

2つの環状列石(かんじょうれっせき)の間に立ってみよう。何が見えるかな? まわりには、縄文(じょうもん)時代を復元した森。遠くには、東に奥羽(おうう)山脈、西に高森(たかもり)山地の山なみが見えるね。復元された掘立柱(ほったてばしら)建物のほかに、現代の建物はひとつも見えないよ。まるでタイムスリップしたみたいだね。
環状列石(かんじょうれっせき)の仕組みと役わり

上:万座(まんざ)、下:野中堂(のなかどう)
2つの環状列石(かんじょうれっせき)に近寄って見ると、二重の円の形になっているのが分かるよ。それに、それぞれに長い石が立ててあるところがあるね。これは、日時計じゃないかと言われているんだ。夏至(げし)の日には、2つの環状列石(かんじょうれっせき)の中心と、この日時計のような石が一直線にならぶ位置に、太陽がしずむことが分かっているよ。季節や時間を知るために作ったのかもしれないね。
「大湯ストーンサークル館」の展示(てんじ)室

遺跡(いせき)のそばには、出土した土器や土製品(どせいひん)などを展示(てんじ)している、「大湯ストーンサークル館」があるよ。マツリの道具と考えられる四角い土版(どばん)は、なんと人間の体を表現しているんだって。
土版(どばん)についている丸いくぼみは、口や目などを表しているみたい。それに、1から6までの数も表しているんじゃないかと言われているよ。縄文人(じょうもんじん)は、数を数えることをちゃんと知っていたんだね。
キャラクター