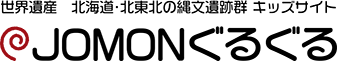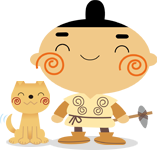伊勢堂岱遺跡[いせどうたい いせき]

[いせどうたい いせき]


北秋田市の、大館能代(おおだてのしろ)空港のすぐ近くにある遺跡(いせき)です。空港への道路を建設しているとき、環状列石(かんじょうれっせき)が3つも見つかりました。さらに、あとからもう1つ見つかり、環状列石(かんじょうれっせき)が4つも集中しているのはここだけです。環状列石(かんじょうれっせき)とは、大きな石を円形にならべた遺跡(いせき)のことで、ストーンサークルともよばれています。お墓や儀式(ぎしき)をするための神聖(しんせい)な場所と考えられています。
4つの環状列石(かんじょうれっせき)の石は、まるで石垣(いしがき)を作るように組まれています。これは、青森県青森市の小牧野遺跡(こまきの いせき)と同じ方法です。環状列石(かんじょうれっせき)の土坑墓(どこうぼ)からは、キノコの形や、うずまきの文様(もんよう)がついた土製品などが見つかりました。土偶(どぐう)もありますが、ほとんどはこわれています。何かの願いをこめて、こわされたのかもしれません。
1体だけ、完全に復元できた板状土偶(ばんじょうどぐう)は、逆三角形の形で、少しとぼけたような顔をしています。これらは、環状列石(かんじょうれっせき)で行われた儀式(ぎしき)に使っていたようです。



環状列石(かんじょうれっせき)Aの石

環状列石(かんじょうれっせき)Aでは、石をよく見てみよう、青・赤・黄色などの色がついた石がならべられているね。石の種類は、20種類以上もあるんだ。どんな意味があったのかな?
環状列石(かんじょうれっせき)Cの作り方

環状列石(かんじょうれっせき)Cでは、作り方を見てみよう。縄文人(じょうもんじん)は、わざわざ土をもって、土手にしたところに石を置いているんだ。限られた道具しかなかった縄文(じょうもん)時代に、大きな土木工事をしていたんだね。
土、日、祝日には、ボランティアのガイドさんが遺跡(いせき)を案内してくれるよ。ぜひ話を聞いてみよう。
キャラクター「いせどうくん」